共有者が行方不明の場合
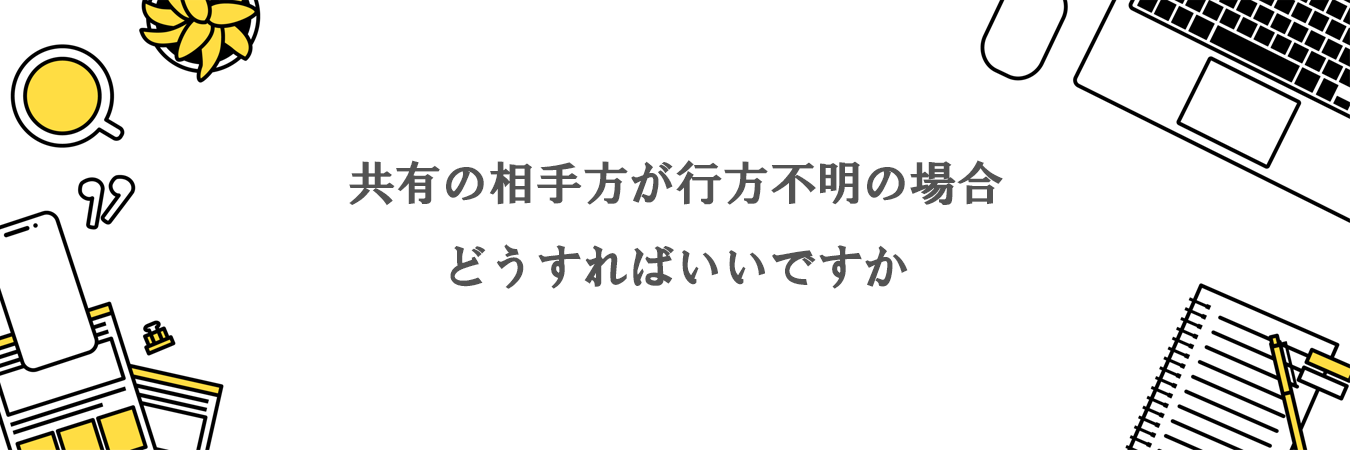
登記簿上の住所から、住民票等公的資料を追跡していき、現在の住所が判明すれば、訴状にその住所を記載し訴訟を提起します。住所が判明しない場合には、公示送達の方法により訴状を送ることになります。
<所在等不明者の持分取得制度>
令和3年の民法改正において、所在等不明者の共有持分の取得制度が条文化されました。 この制度は、所在等が不明な共有者がいる場合に、その持分を時価相当額で取得することを認めるものです。 裁判所が定めた共有持分の時価に相当する金額を共有者が供託し、所在等不明者の持分を強制的に取得します。 所在不明者の持分取得制度を利用する場合、裁判所は所在不明者等の権利主張の機会のために公告を行うとともに、他の共有者にも持分取得の機会を付与するため通知をすることになります。
<所在等不明者の持分譲渡権限の付与>
令和3年の民法改正において、所在等不明者の共有持分を他の共有者全員と第三者に対して売却するための権限を付与する制度が創設されました。 共有者の一部の所在等が不明な状況で、共有物全体を売却する際にこの制度を使えば、一部の共有者の所在等がわからなくても第三者に売却することが可能となります。 ただし、裁判の効力が生じてから2か月以内に譲渡する必要があります(例外的に裁判所はこの期間を伸長することができます。)。
執筆者等

- 吉藤真一郎
- 弁護士
- 共有物分割請求、借地非訟などの不動産案件、相続案件などを多く取り扱っている。

- 幡田宏樹
- 弁護士・公認会計士
- 企業法務、同族会社(非上場会社)に関する問題、共有不動産に関する案件に取り組む。
